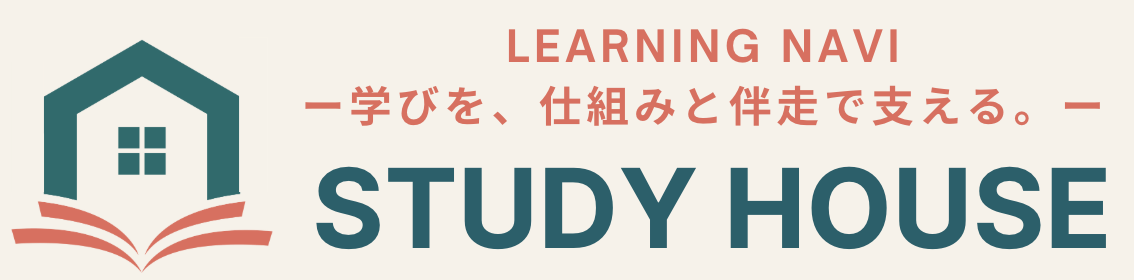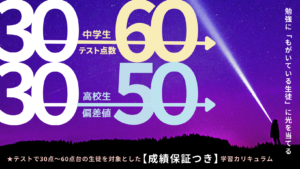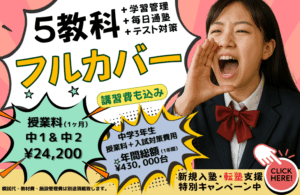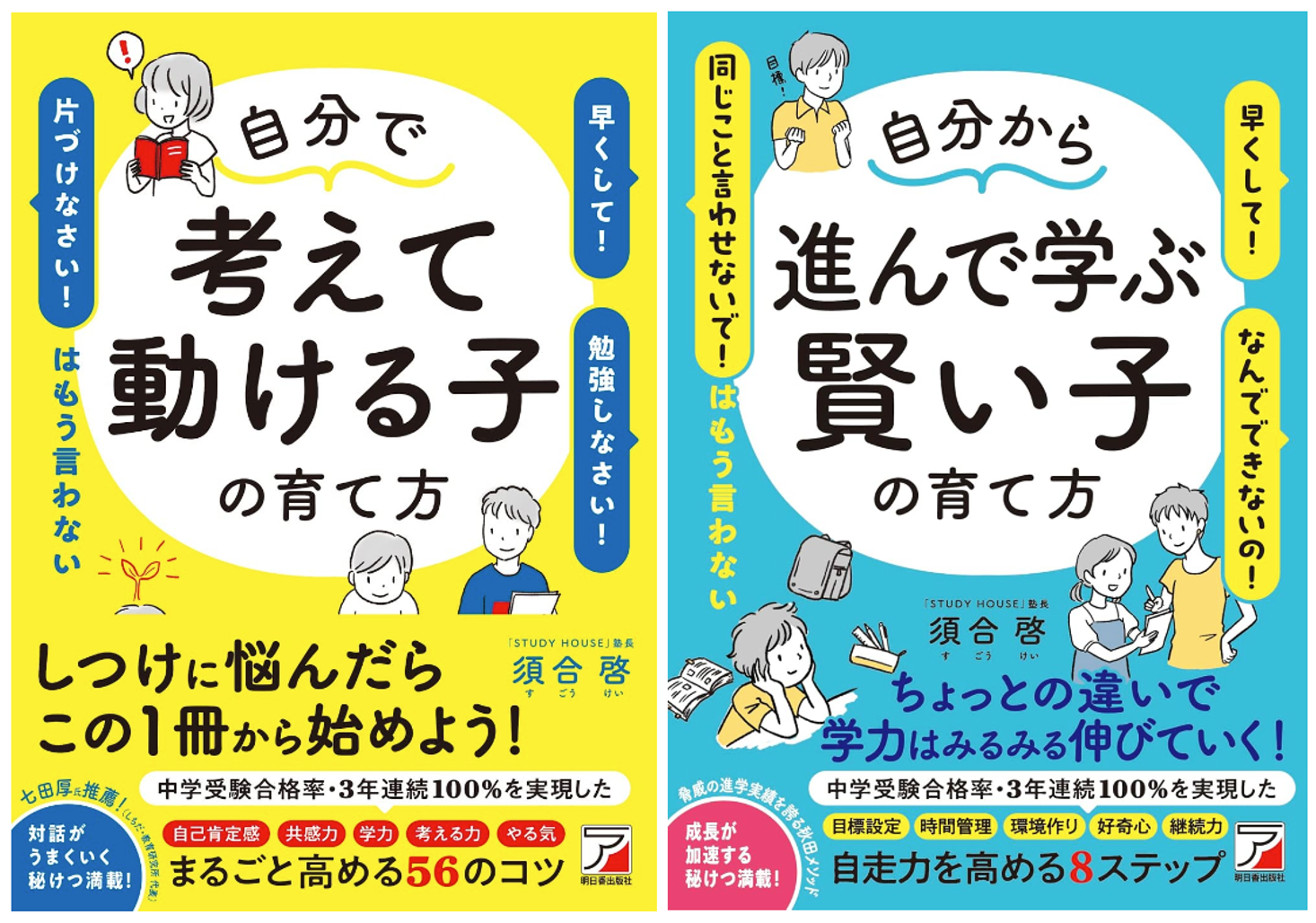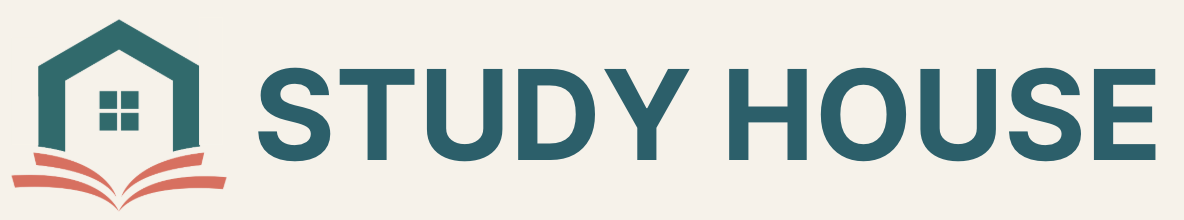テスト点数30点〜60点/偏差値30〜50の生徒対象
【成績保証つき】学習管理型個別指導プログラム
↓
中学生|月額定額「¥24,200(授業料)」で5教科履修コース開講!
〜夏講習・冬講習での加算額なしで毎月定額で通塾可能〜
↓・↓・↓詳細はこちら又は「LINEへ」↓・↓・↓
ーーーーーーーーーーーーーーーー
おはようございます。
長坂です👩
7月も半ばを過ぎ、
いよいよ夏休みが目前に迫ってきました。
楽しい予定が詰まっている子も、
そろそろ学校から出されているであろう宿題を
持ち帰ったまま、手をつけていない子もいるかもしれません。
今日は少しだけ先の話。
夏休みが終わってから、
冬休みまでの間の大切な学期の過ごし方について、
そして算数・数学の「ここは絶対に押さえておいて!」
という単元と学び方について書いてみますね。
みなさんは
「ファーストペンギン🐧」
という言葉を聞いたことがありますか?
群れの中で、
天敵がいるかもしれない海へ、
勇気を出して一番最初に飛び込むペンギンのことです。
怖いけれど、
一歩踏み出したそのペンギンがいるからこそ、
他の仲間も続いていくことができる。
勉強でも同じです。
クラスの誰よりも先に宿題を終わらせる。
わからないことを一番に質問する。
テストが返ってきたら、
できなかったところを一番に解き直す。
誰かの一番乗りは、
周りにも良い影響を与えます。
でも、一番得をするのは、
勇気を出して動いた本人です😆
夏休みが終わり、
秋から冬にかけての学期は、
学校でも塾でも
「基礎の総仕上げ」と「応用の入り口」
が交わるとても大事な時期。
学年が進むにつれて差がつきやすいのも、
この秋から冬にかけて。
特に算数・数学は、
夏以降に学ぶ単元がとても大切です。
小学生なら「小数・分数」「割合」「速さ」
中学生なら「方程式の応用」「関数」「図形」
などなど。
ここをおろそかにすると、
後の単元で「なんとなく」では乗り切れなくなります💦
苦手に感じている子ほど、
「一番に」手をつけてほしい。
問題を解いて、
わからなければ声を出して質問する。
答えを写して終わらせず、
「なんでこうなるのか」
を誰かに言葉で説明してみる。
これが、算数・数学の理解をグッと深める方法です👍
この夏休み、そして秋以降も、
「ファーストペンギン」でいる勇気を🐧❗️
STUDY HOUSEの通塾生限定の夏期講習では、
できるだけ先の学習までの予習と、
ここまでの復習を徹底してサポートしています。
夏に一歩踏み出しておくことで、
秋からの「わからない」を減らし、
自信を持って新しい単元に挑めるように。
学校の宿題だけじゃなく、
「わからない」をそのままにしない習慣を、
一緒に育てていきましょう🌱
夏の次の一歩を、
誰よりも先に踏み出せる子を
STUDY HOUSEは応援しています📣🌻
Enjoy the Challenge at STUDY HOUSE. 〜挑戦を、楽しめ!〜
現在、中3生・保護者様からのお問い合わせを多くいただいております。
実際のSTUDY HOUSEの雰囲気や学習内容を体験してみませんか。
お気軽にお問い合わせください!
![]()
ーーーーーーーーーーーーーーー
秋田県公立高校入試「合格最低基準点」について
【詳しくはココをクリック👍】
ーーーーーーーーーーーーーーー

【STUDY HOUSE】
「正しい勉強法」と「学習習慣」が身につく学習管理型個別指導塾
✅STUDY HOUSEの基本料金コチラ💁
✅[実績]
・(中3)全県模試【総合1位】を4年連続獲得
・医学部医学科4年連続【現役合格】
・国際教養大学【3年17名合格】

ーーーーーーーーーーーーーーーー
合格率100%
STUDY HOUSEが全面プロデュースする
「秋田高校合格専門塾」

秋田高校合格に特化したサービス・カリキュラム
ーーーーーーーーーーーーーーーー
YouTubeチャンネル
「ホームルームTV」<高校大学の進路相談&学習プラン>もお願いします🙏

ーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーー
【国語読解:個別添削コース】
教科の基礎となる読解を日々実践しませんか?
STUDY HOUSEでは通塾するすべての生徒が国語読解の個別添削を受けています。
<詳細ページ>
https://study-house.jp/kokugo-dokkai/
専任講師の添削指導にて、これまで偏差値40台生徒が偏差値65越え&難関中学・高校、難関大学・高校への合格・進学を果たしています。
国語も数学同様に解く際のルールがあります。
是非、STUDY HOUSE国語読解メソッドをマスターして国語を得意にして
安定した成績を手に入れましょう!
+++++++++++++++
STUDY HOUSE 国語読解の効果
+++++++++++++++
▼各段落の要約を掴める
▼筆者の主張と人物の心情を掴める
▼「対比」と「因果関係」を掴める
▼記述力が身に付く etc
・
・